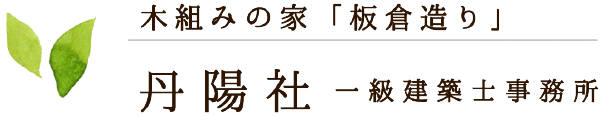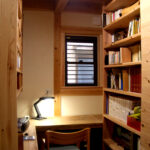2008年06月
板倉造りの家
桜の木が家族を暖かく見守る、大好きがいっぱい詰まった木の家

| 家族構成 | 大人5人+子ども1人(2世帯住宅) |
|---|---|
| 建物概要 | 木造2階建て/板倉造り |
| 延床面積 | 165.6㎡ |
| 竣工 | 2008年6月 |
ポイント- Point -
板倉造りの家を建てるきっかけは・・・・・
K様が住まいの建て替えを決心されたのは、お父様からお祖母様も入れて大家族で一緒に住まないかと相談されたからだそうです。今まで3世代に渡って住み続けた家族の思い出が残っている家に替わって新しく建てる家は、4世代以上、少なくとも120年から200年暮らしていける住まいにしたいという事でした。
また、K様自身が少々アレルギー体質をもたれていましたので、木材を始めとした自然素材を使うという事も必須の条件でした。木材の特徴である保温性や調湿性は、住まいの環境として最適である事も勉強されていてご存知で、木造住宅を建てるという事は決められていました。
当社へは、HPで板倉構法に興味を持たれ、訪ねてこられました。
実際に建っている板倉造りの家を見学していただき、当社の勉強会にも参加して下さいました。
板倉構法で建てる家は非常にシンプルで、金物は極力使わず、無垢の木組みで建てる構法で日本の古民家を見ても適切な補修をしてゆけば、100年以上持つ耐久性は実証されてると理解していただき、私たちが手がけている「伝統構法板倉造りの家」を選んでいただきました。
構造のポイント
日本の伝統構法である板倉構法、柱に溝を彫りその溝に杉無垢材を落とし込みます。
K様邸では、通し柱5寸(ヒノキ)、大黒柱8寸(スギ)、管柱4寸(スギ) 国産無垢材を使用しました。
床・壁・屋根などは、基本的に厚さ3cmの杉無垢板を使用しています。
無垢材と遮熱シートが断熱材の代わりになり、一般的な断熱材は使用しません。
一般的な在来構法の約3倍の木材を使用し、できるだけ構造金物を使わず木組みや込み栓を使い耐久性に優れた伝統的な民家の特徴に基づき、長寿命の住まいを目指しました。地震に対しても、伝統構法の特徴を生かし「地震力の剛の力」に対して「揺れるが倒れない柔の力」で抵抗し、地震に強い性能を保ちます。
デザインのポイント
 ご要望が「大正ロマン風」ということで各所に和洋の意匠を取り入れています。
ご要望が「大正ロマン風」ということで各所に和洋の意匠を取り入れています。
伝統的な和の要素である柱が内装露出した真壁(しんかべ)と木製の引戸を採用する一方、窓や照明は洋風のアンティークなデザインのものを選びました。
アイアン製のシャンデリアの暖かい光で照らされることで、それぞれの要素がエレガントに調和しています。
また、K様のこだわりで全体的に左右対称(シンメトリー)な構造・デザインとなっています。
板倉造りの特徴である杉の無垢材が内装の仕上げとなっていることにより、住まい手とともに時を重ねてゆくたびに深みを増していく家となっています。
お客様の声- Voice -
お客様がブログを公開されています。
K様は、ご自身のホームページで家づくりの全てを「さくらの家日記」として公開されています。
読み応えのあるホームページで、家づくりをお考えの方は、大変参考になると思います。
K様の本音が包み隠さず書かれています。
お客様の声(K様の家づくり日記「さくらの家日記」より)

最初は家の構造さえ全く知らなかった所からの出発だったが、沢山の出会いに恵まれてこの日を無事迎える事ができた。丹陽社のオカ所長、Hさん、Uさん。業者選定の時期から考えたら1年間、最初から最後まで常に全力投球で”さくらの家”を造りあげてくれた、私達の家造り最高のパートナー。
住み心地の良い家を造るだけだったら丹陽社以外の会社でもできたと思う。でも、柱の一本一本、材料のひとつひとつまで提案してくれて、素人の私達の希望を根気良く聞き続け、プロの視点で形にしてくれた・・・これは丹陽社でしか出来ない事だったと思う。
そのお陰で私達の家は壁や柱や建具のひとつひとつに色んな人の気持ちが篭り、物語ができた。だから、新しい家に移って1ヶ月経つけれど未だに「ここをこうしておけば良かった」といった後悔がまだ全くない (今後は多少は出てくると思うが・・・)。これは凄い事だと思う。途中私も全身全力で家造りに向き合ってきたから、主張がぶつかる事もあったし厳しい話もさせて貰った。敢えてこのHPでもすべてそのまま書いてきたけれど、それに対しても真正面から受け止めて真摯に対応してくれた。
私達の”さくらの家”は丹陽社なくしてあり得なかった。
1年前、丹陽社に出会えて本当に良かったと思う。
この前四歳になったばかりの息子は、住宅展示場から勉強会、徳島から静岡まで、常に私と一緒に家造りに参加してくれた。
私は祖母から君まで四世代でこの家造りができた事がとても嬉しく思っている。皆で造ったこの家を大事にして欲しいし、先の事はどうなるか誰も判らないけれど、できれば君の子供や孫が何十年後にこの家を走り回っていて欲しいなあ・・・と思う。