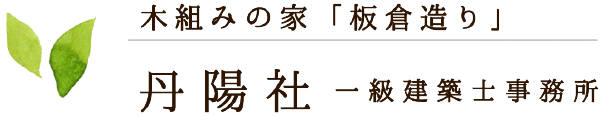Itakura
伝統構法「板倉造り」
- HOME
- 伝統構法「板倉造り」
日本の風土に適した日本の家

板倉造りは伊勢神宮や正倉院に代表される日本の伝統構法です。柱や梁を木組みで構成し、4寸角(120㎜)の柱に溝を掘り、厚さ1寸・幅5寸の厚い杉板を落とし込んで一体の壁をつくります。大切なものを守るための蔵として使われてきた板倉造りは、風雨や寒暑をしのぐだけでなく、木組みの柔らかさを生かして大きな地震の揺れにも粘り強く耐えます。板倉造りは、気候風土適応住宅にも認定された、日本の気候風土に適した、災害に強い伝統構法なのです。
Features
板倉造りの家の特徴

揺れても崩れない。
地震に耐える家
伝統的な継手・仕口で組み、金物を極力使用しない木組みの構造です。地震に対して全体が揺れることで地震の力を吸収・分散し、揺れを受け流します。それにより、地震で変形しても倒壊することのない、修復できる家になります。
優れた調湿・断熱・保温効果。
人にも自然にも優しい家
板倉造りは通常の木造住宅の3倍ほども木材を使用します。構造材をそのまま内装の仕上げとすることで、無垢の杉材の持つ調湿性・蓄熱性を最大限に発揮させます。調湿によってカビやダニの発生を抑制し、ハウスダストやアレルギーの症状を抑える効果が期待できます。また国産材を多く使うことは森林の保全やCO2の吸収・固定にも役立ちます。


暮らしをまもる。
火災に強い家
木は意外にも燃え尽きるのに時間のかかる素材です。厚い杉板は表面が炭化することで難燃層をつくり、炎の熱に耐えることができます。板倉造りは900℃に達する加熱防火試験を経て、防火構造として国土交通大臣認定を受けています。
板倉造りの性能をデータで
裏付けるのも、私たちの役目です。
丹陽社は日本板倉建築協会に所属し、板倉造りの普及のための試験に協力しています。
壁倍率の大臣認定を取得
地震による横方向の揺れに耐え、変形をとどめるのは柱ではなく耐力壁と呼ばれる部材です。耐力壁はその強さを斜めに筋かいを入れた壁と比べて何倍の強さを持つかという壁倍率で評価されます。板倉造りは、落とし込み板を木摺りで補強する木摺りタイプと、吸いつき桟で補強する桟付きパネル式それぞれについて、落とし込み板壁の壁倍率で国土交通省より大臣認定を取得しています。
| 壁タイプ | 壁倍率 | 認定取得 |
|---|---|---|
| 木摺りタイプ | 2.2倍 | 平成19年5月 |
| 桟付きパネル式 | 3.4倍 | 平成19年05月 |

防火構造の大臣認定を取得
平成19年5月に壁倍率を有する木摺りタイプの木摺り板(24㎜)と、落とし込みの厚板(30㎜)を合わせて、総厚さ54㎜の壁を構成し、防火構造の要求性能である30分間の延焼防止性能を確保しました。これにより、2階建住宅において準防火地域(床面積500㎡以下)、法22条区域(床面積3000㎡以下)の延焼のおそれのある部分の外壁を木材だけで構成した落とし込み板壁で設計・施工することが可能になりました。