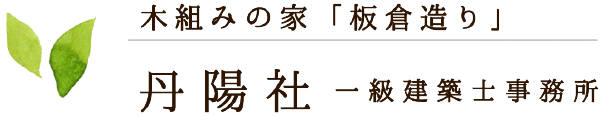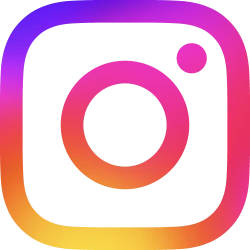2025年09月01日
板倉造りに出会うまで【オカの板倉奮闘記1】

丹陽社は板倉造りを中心としてお客様の健康を考えた健康住宅を建てている設計事務所です。
一級建築士で当社の代表であるオカが、いかにして板倉造りと出会い、建てるようになったのか。
そこまでに至る経験を3回に分けてお送りします。
第1回はオカが順調だった輸入住宅の設計から離れた理由。そして板倉造りとの出会いです。
輸入住宅との出会い

「ちゃんとこちらの要望を聞いて動いてよ!!」
「こちらのいう事に、すぐに対応できないのなら、うちでは必要ないんだよ。」
私は頭にきました。
輸入住宅を始めたときの親しげな態度と裏腹なものすごく高圧的な言い方だったからです。
私は、前々からこの会社の仕事の方針に腹が立っていたのです。
「わかりました。私には無理かと思います。失礼します。」
「売り言葉に買い言葉」頭の中でこのフレーズが何度も浮かびました。こうなれば、今やっている大体出来上がっていた仕事の設計代金ももらえません。
そうです。これまで、仕事をくれていた取引先はなくなってしまったのです。これから新しく仕事を取っていく工夫をしなければなりません。
「えぇ!どうするんだよう。」
「あ~ぁ、しかたないなぁ・・・・・。」
それは、2005年の春のことでした。これで私は、輸入住宅の設計をやめることに踏ん切りがつきました。これをきっかけに、まだ実績のない板倉造りの家を中心に仕事をしていこうと決心したのです。
話は過去に戻ります・・・・・・・。
独立して数年が過ぎた2000年。時たま住宅の設計施工の仕事も入り、自分なりに納得して仕事ができるなと思っていた頃でした。
デザインなんかも、いろいろな雑誌を読み、できるだけこれから始まる21世紀のトレンドを取り入れようと心がけていました。また住宅の基本的な性能に関しても、いろいろな工法を調べていて何か他ではあまりやっていない、いいものがないかと探していたんです。
そんな時、取引先のN工務店さんから、輸入住宅のバイヤーをしているKさんを紹介されました。
「オカさん、輸入住宅の設計をしてみる気ない?」
「今まで、エジプト人のデザイナーにプランをしてもらってたんだよ。」
「でも、言葉も充分通じないこともあるし、確認申請をはじめとして実施図なんかは改めて日本の設計事務所に頼んでいたんだけどそのエジプト人は忙しくなって手が回らなくなってしまったんだ。」
「それで、デザインができて確認申請までしてくれるところをさがしているんだけど・・・・。」
そういう風に、Kさんは切り出されました。
でもホントは、二度手間なので経費を節約するために日本の設計事務所でデザインと申請をしてくれるところがないか探しているということだったんです。
「輸入住宅?エジプト人・・・・・?」
「海外の住宅の性能のいいのは聞いています。私にできるかどうか調べさせてくれますか?」
話を聞いてちょっとびっくりしたんですが、一般的に輸入住宅といえば日本のツーバイフォーの元になった工法です。日本のツーバイフォーよりも大きな断面の木材をつかう北米の工法という基本的なことだけは知っていました。つまり、本格的な北米式の枠組み壁工法の輸入住宅の設計をするつもりが無いかという問合せなんです。
バイヤーのKさんにいろいろ質問をしました。そして自分でも本を買って調べてみました。ジェトロが輸入住宅の促進に力を入れていることもわかりました。
日本の住宅にはない気密性に優れています。
そして日本の軸組工法ではできない斬新なデザインができる可能性があると思いました。
これはひょっとして今まで求めていた建築かもしれないと思ったんです。
そして、アメリカやヨーロッパと文化が違うアラブ系のエジプト人が設計しているなら欧米文化が身近な日本人の私でもできるだろうと思いました。
「面白そうですね。いいものができると思います。やらせてください。」
何日かしてから、ちょっとしたデザインをしたものをもっていき、返事をしました。そうして話はとんとん拍子に進んだのです。
それをきっかけに大阪南港にあるジェトロ輸入住宅部材センターを度々訪れ、輸入住宅の勉強をするため関連するセミナーに参加しました。その当時は、通産省の補助事業として、輸入住宅を普及するために国が力を入れていたので、輸入住宅の技術の習得のためのセミナーは割合、安価に簡単に参加できたのです。
そして、具体的には輸入住宅のバイヤーのKさんといろいろ協議しました。実務的なことは、Kさんの紹介のカナダ人の大工さんと一緒に、つめていきました。
それは、技術に関してもデザインに関しても私にとっては目新しくすごく刺激的でした。中途半端なものをしたくなかったので、カナダの本格的なものを求めたんです。でも、日本の考えを多少取り入れて住みやすい工夫をしました。
そうして、一戸建ての住宅を手がけていくようになったんです。
やってみて改めて思いました。
これは、気密性にも優れ、構造的にも強い壁で建物をささえているな。
日本の木造建物の2倍もの木材を使うし、金物でがっちり固めている。
地震国日本に必要な耐震性に優れているな。
デザイン的にも欧米の洗練されたデザインを持っている。
うーん、やっぱり、やるのなら本物だなと。
でもこのとき、強く引かれたこの長所が、やがてこの工法から私を引き離す短所に見えてくるのです・・・・・。
シックハウス

輸入住宅のバイヤーのKさんから輸入住宅を建てたいとおっしゃるお客様を紹介していただき、さっそく設計に取り掛かったんです。
プランの打ち合わせはうまくいきました。
お客様とはいろいろな考えを検討していいものが建つなと思えました。
確認申請で少々手こずりました。
構造用金物が外国製で基準に合わないと。メーカーの耐力証明をだすか、金物の耐力審査をしてほしいと役所に言われました。輸入元に問い合わせ、日本のツーバイフォーの金物の基準となっている製品だということがわかり、説明書を取り寄せ何とか収めました。
建方はカナダ人の大工が二人頑張ってくれました。
日本の釘打ち機よりも一回りも大きい重い釘打ち機を縦横に使いパワフルな作業はテンポよく進みます。
材木も2インチかける6インチ、8インチ、10インチなど厚みは5センチですが、幅が15センチ、20センチ、25センチの材なんです。日本の現場が繊細な作業に思えるほど、迫力ある作業です。
今は、板倉造りをしていますので、国産杉材でそれぐらいは当たり前に見かけますが、当時はそれらを目の当たりにしてびっくりしましたね。
建った建物は、輸入住宅独特の斬新なデザイン。
カラフルで街並みににはちょっとそぐわない気もしましたがお客様も私たちも満足していました。
バイヤーのKさんに仕事を紹介されてしていくことになったんです。
そうこうしているうちに、縁がありまして分譲住宅をしている不動産屋さんが私たちがやっている輸入住宅に目をつけられて、仕事をいってくるようになりました。これが、私たちのお得意様になったのです。
でも、ちょっと気になることがありました。
この住宅は、木の化粧材にペンキを塗って仕上げるのです。
はじめは、木製建具や周り縁、幅木などをいちいち塗装して手間をかける欧米のやり方に感心してました。日本の今の住宅のほとんどは表面を塩ビなどでコーティングした工業製品を使っているからです。
でも建物の気密性がいい分、塗料のシンナーなどの溶剤のにおいが結構残るのです。
これは健康のために良くないような気がしてきました。
いろいろ気になって調べていると、健康に良くないのは塗料などから発生する化学物質だけでないのです。
気密性が高まると結露が起きやすく、カビなどが発生する原因となることがわかりました。日本の気候は、湿気が多くその対策を怠ると、建物だけではなく住む人の健康に対しても悪い影響があるのです。
そして、この輸入住宅の壁耐力を構成する構造用合板、この合板を張り合わせている接着剤からも人体に良くないホルムアルデヒドが発生していることも分かってきました。
その頃はシックハウスという言葉も、一般的にあまり知られていなく、結露対策も真剣に考えられていなかったようなんです。なぜなら、今までの日本の住宅は隙間だらけで、空気が常に出入りして、換気や結露とは無縁の環境だったからです。
建築のこだわり? 私のこだわり?
欧米式の枠組み壁工法による輸入住宅が、向こうのやり方そのままでは、四季があり湿度の高い日本になじまないと思い始めたとき、いろいろなことが気になりだしました。
建物を作るに際して、外人は粗い。たまたま、使っていたカナダ人大工がそうだったのかも知れないんですが…
たとえば、階段をかけている壁と階段の間がすいている。それも上と下とで、ひらいている幅が違っている。
これは、施工精度が悪いことを示しています。何度指摘してもカナダ人の大工は、なんでそんなことを言うんだというような顔をするのです。
建具の枠や周り縁、幅木などの化粧材の上から平気で釘うちをする。あとでペンキをするからかまわない。というんです。でも、よく見ると釘の頭が見えるのです。日本の繊細なモノつくりとは考え方がちょっと違います。
「ノープロブレム!!!」
私が指摘すると、いつも問題ないとカナダ人は言うのです・・・・・・。
確かに機能的には問題はないのです。ただ見た目には良くない。私は経験的に見た目に良くないものは、今すぐではないけれど必ず何らかの良くないことの原因になるように思うからなのです。
このカナダ人も頑固です。自分のやり方を替えたくないのです。そこは、どこの国の職人さんも同じです。
また、発注先の不動産屋さんから、いろいろな注文が出てきました。
今までは、輸入住宅自体をよく知らなかったので、こちらに任せていてくれたのですが、何棟もやっているうちにいろいろと経済的な要望?というか細かい指示がでるようになってきました。建設的な意見だけならいいのですが、それ以外の注文もかなり出るようになってきたんです。
ある日、構造体が上がったので、行ってみると屋根の勾配の形状が変っている。変だなと思って、図面と比べてみると屋根を支える登り梁の長さが短くなっている。
つまり、屋根の勾配が緩やかになってくるのです。
当然、高さも変わってくるわけです。小屋裏の天井も低くなり、使い勝手に大きな差が出てきます。デザインもスマートさがかけて、ずんぐりしたような印象になってしまいました。
「おい!この登り梁、寸法が間違っているぞ!!すぐ、取り替えるように手配してよ!!!!」
「図面どおりじゃないと、検査も通らないよ!!!!」
現場の大工はもそもそ言っています。どうやら、部材の寸法をワンランク落して、発注していたんです。
この件は、バイヤーには事前に連絡済みでした。もちろん発注者の不動産屋にはバイヤーからうまく言っていたようです。構造的には問題はないのですが、もし、検査で指摘されれば部材を代えるか図面を訂正しなければなりません。(今では、絶対に考えられないことです。)
確かに部材、一本一本を計らねば、じっくり図面と現場を見比べなければ違いはわからないです。私は、図面を描いていますからすぐわかりましたが、はじめて現場にきて短時間見ただけではわかりません。案の定、その件は指摘されないまま検査は通りました。
このようなことは、いろいろあったほんの一部です。
カナダ人やバイヤーは、このやり方のどこが悪いんだというような顔をするし、発注先は今やっている仕様について、お金がかかるそれ以上のことはもってのほかで、改善なんてとんでもありません。むしろ、それ以下のやり方をさせかねない勢いでした。
そんなこんなで、この仕事に情熱を失いかけていました。ただ、生活の糧としては、この輸入住宅は大きな部分をしめていました。この仕事をなくすことは、私にとっては大きなダメージになります。なんとなく、悶々とした日々をすごす毎日でした。
業者の下で仕事をするのは耐えられないな~。
板倉構法との出会い

不動産屋さんの仕事は嫌だなぁと思い始めていましたが、今や受注の柱となっています。この仕事を辞めるのは忍びないなと考えていました。
ぼんやりと思い始めていました。
「お客さまの顔の見えない分譲住宅の仕事はあまり向いていないなぁ。」
「やっぱり、会社じゃなくて、住む人と直接やり取りができて良いも悪いも話し合って進める仕事が自分にはあっているなぁ。」
「職人さんとも直接向き合って、動いてもらうことが必要だよな。」
実際、サラリーマン時代からわがままな私は上から一方的に言われるのは我慢できない性質でしたから・・・・・・・。
また、輸入住宅はそのままでは日本には合わないと思っていました。そして構造的に強く、断熱性に優れてシックハウスの影響の少ない、人にやさしい家を造りたいなと考え始めたのです。
2004年の暑い夏の日の昼休み、何気なく今日送られてきた建築雑誌をパラパラとめくっていました。ふと、目に留まったのが木造のいろいろな構造の耐震実験の記事でした。その中の記事に板倉構法という名称が出てきました。
四寸角の杉の柱に厚さ30ミリの杉板を落としこんで壁を形成する、日本の伝統構法だそうです。
実験結果では思わしい数値が出なかったようなんですが、他のよりよい結果が出た構造よりも、この「板倉造り」という構法に強くひかれました。(そのときは、知らなかったのですが日本の伝統構法では、構造自体がゆれて地震力を吸収するという働きを持つため、建物をゆらさないための剛性を保たせる実験では数値が低いのは当然なことなんでした。これは、今まで考えていた耐震性とはまったく違う考え方で、地震国日本にうってつけの構法だと感じました。)
さっそく、雑誌社に詳細を問い合わせました。
そうすると、詳しいことは開発された筑波大学の安藤邦廣教授に訪ねてほしいという答えがかえってきました。突然で失礼かとは思いましたが、安藤教授の研究室に電話をしたのです。たまたま、夏休みにもかかわらず安藤教授は研究室におられ、お話することができました。
そのとき、雑誌を読んだことを話し、「板倉造り」に興味があるという事。
そして、今やっている仕事の話などをさせていただきました。
ちょうど、お出かけになる前だったらしく、気がせいておられたようで、みなまで聞かれず、すぐさまお答えになられました。
「東京で勉強会をやっているので興味があるのだったら、参加してはどうですか?詳しいことは担当のものに聞いて下さい。」と、お誘いがありました。
「東京・・・・・・。」と思ったんですが、詳しく知るためと思い直し安藤先生の主催される「伝統木造研究会」に入れていただくこととなりました。
あとで、聞いたんですが研究室に電話をかけても、先生がつかまることはめったにないことで、すごくラッキーなことだったみたいです。
オカの板倉造り奮闘記2につづく
「丹陽社モデルハウス見学会」
弊社所長オカが初めて建てた板倉造りである丹陽社のモデルハウスの見学会です。
板倉造りの家に住み続けてわかったこと、経年変化や木の家のお手入れのこと、なんでもお聞きいただけます。
家を建てるなんて考えてない……でも大丈夫です!
無理なセールスはいたしません。
板倉造りの家を見て、触れて、知ってください!